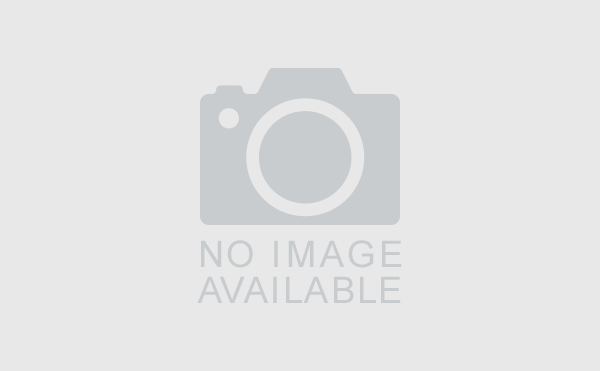++++++++++++
今日のテーマはこちらです↓
=============
受験生・保護者に知っておいてほしい!
<受験校の決め方〜ステップ1具体例>
=============
受験校の決め方シリーズを続けています。
前回は、受験校を決める3ステップの
「ステップ1」について解説しました。
今回は、ステップ1のポイントを使って
どのように受験校をピックアップしていくか。
具体例をお伝えします〜
まずは復習から始めましょう!
★ステップ1★
様々な角度で大学ごとの問題を分析する
・偏差値(どのゾーンの大学なのか)
・出題形式(マーク式なのか記述式なのか)
・問題の傾向(難しい問題なのか標準的な問題なのか)
・求められる力(スピードなのか思考力なのか)
記憶が戻ってきましたでしょうか?
それでは具体例を解説していきますね。
<具体例:順天堂大学 一般入試>
〜分析〜
【偏差値】
・70(河合塾)*模試受験者の上位2%のゾーン
【出題形式】
・全ての科目で、マーク式と記述式両方の問題が出題される。
【問題の傾向】
・数学は、典型問題に併せて難しい問題も出る。
・英語は、600〜800語の長文4題と自由英作文1題が出題される。時間は80分とタイト。
【求められる力】
・全部の科目で、思考力が問われる問題をタイトな時間で解く力が求められる。
・思考力とスピードのバランス力が問われる。
・英語は、読む力と書く力の両方あることが求められる。
・数学は、「閃く」力も必要。
【その他】
・科目配点は、英語:数学:理科(2科目)= 200点:100点:100点
・英語得意な人が有利な配点条件
〜判断〜
・河合塾の模試で偏差値65以上取れていれば、候補に入れる。
・英語の偏差値が65以上であるかどうかがポイント。
・理由は英語の問題が難しい上に、配点が高いため。
・理系科目での逆転を狙いにくい。
・英語力の有無が受験校に入れるかどうかの判断基準となる。
こんな感じです〜
紙面上の制限があるので、
ちょっと堅苦しい言葉になってしまってすみません。
こうやって問題分析することで、
○ 自分がどういう力をつけていけばいいか
ゴールもわかってきます。
ちょっと手間がかかりますが、
欠かせない作業だと思います。
ぜひやってみてくださいね!
.png)