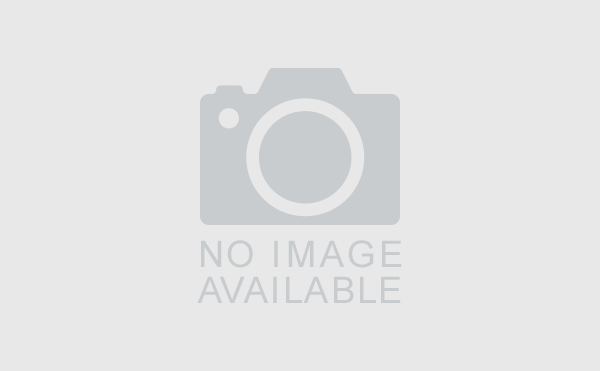今日のテーマはこちらです↓
=============
受験生・保護者に知っておいてほしい!
<模試の後何する?>
=============
≪模試の後にやる必要があること≫
1、丸つけをする
2、学習範囲の得点率を出す
3、振り返りをする
4、課題に対する具体策を考える
5、講師に「4」が合っているか確認する
6、4を実行する
今回は、
「2、学習範囲の得点率を出す」
を解説していきます〜
一瞬「????」
となる部分ですよね。
しっかり説明していきますね〜
模試の得点を出した時に、
「全体の得点」だけ
見て落ち込んでいませんか?
えーーーーーーー!!!!
それがフツーですよね???
違うんですか???
実はもう1つ。
付け加えた方が
いい視点があるんです。
それが・・・
◯ 授業で習った範囲の問題が満点かどうか
全部できていないとダメなんじゃないですか???
最終的には、トータルで
このぐらいになっておこうね。
という基準はあります。
けど、今の時点では
全体でパーフェクトの状態に
なっていなくて全然大丈夫です。
逆に今の時点で全体で90%取ってないと
いけないとかなったら、
現役合格できる人が
ほぼ全滅状態になっちゃいます 汗
実際そんなことないですよね?
現役で合格している人もたくさんいます。
でもでもでも!!!!
浪人生は全範囲終わっているんだから
全部できてないといけないですよね?
全部できていたら
そら〜有利ですよ。
でも、全部の範囲完全じゃないから、
もう1年勉強しようってなったんですよね?
入試が終わってから2ヶ月。
前の年にカバーできなかったところを
この短期間で完全にするのは、
一握りの天才だけです。
今は全部の範囲完全じゃなくて
大丈夫!
大切なのは、
◯ 授業で習ったところを完璧に解けたか
ここができなかったら
全力で悔しがってください。
意外とできていない人、
多いですよ〜〜〜 汗
ということで、
得点率の出し方行ってみましょう!
===========
<学習範囲の得点率の出し方>
=ステップ1=
授業(予備校 もしくは 高校)で習った範囲の
問題を書き出します。
大問ごとにまとめていきます。
例)数学IA
大問1:【1】確率→全部、【2】場合の数→(1)、(2)
大問2:三角比→全部
=ステップ2=
1で書き出した問題の配点を計算します。
これも「大問ごと」に出していきます。
例)数学IA
◆大問1:【1】確率→全部→10点、【2】場合の数→(1)、(2)→15点
合計=25点
◆大問2:三角比→全部→20点
合計=20点
=ステップ3=
1で書き出した問題で自分がどれだけ得点できたかを計算します。
これも「大問ごと」に出していきます。
例)数学IA
◆大問1:【1】確率→全部→5点、【2】場合の数→(1)、(2)→0点
合計=5点
◆大問2:三角比→全部→20点
合計=20点
=ステップ4=
学習範囲の得点率を出します。
これも「大問ごと」に出していきます。
「ステップ3」の得点を、「ステップ2」の得点で割ります。
そのあと100%換算しましょう。
例)数学IA
◆大問1:【1】確率→全部【2】場合の数→(1)、(2)
・ステップ2:合計=25点
・ステップ3:じぶんの得点=5点
↓
↓3の得点÷2の配点
↓
学習範囲の得点率=20%
◆大問2:三角比→全部
・ステップ2:合計=20点
・ステップ3:じぶんの得点=20点
↓
↓3の得点÷2の配点
↓
学習範囲の得点率=100%
=ステップ5=
得点率が低い順に上から並べる。
1番上にある範囲から
優先して解説を読んでいく。
例)数学IA
◆大問1:【1】確率 【2】場合の数 =得点率 20%
◆大問2:三角比 =得点率 100%
つまり、
「大問1」から復習していく。
大問1の中でも、
「三角比」が取れていない。
ここが弱点の一つ。
三角比を優先して復習していく。
===========
学習範囲の得点率を出すことによって、
「復習する優先順位」
をつけることができます。
優先順位をつけると、
必要なところに時間を
割くことができます。
なので、
「苦手なところに強制的に向き合う」
時間を取ることができます。
学力が伸び悩む原因の一つは。
● 自分が嫌なこと(=苦手なこと)に
向き合うことができない
つまり
苦手範囲の学習はせずに
得意なところばかり解いて、
●やっている気になっている
こういうサイクルを
回してしまっています。
できているところをやっても、
得点は伸びません。
”できないところ”の中から
”できるもの”を一つでも多く作る。
だから学力が上がりますし、
模試の得点にも反映されていくんですよ〜
模試の得点を見るときは、
◯ 習ったところが満点か?
優先して考えると
合格できる受験生になれますよ。
.png)