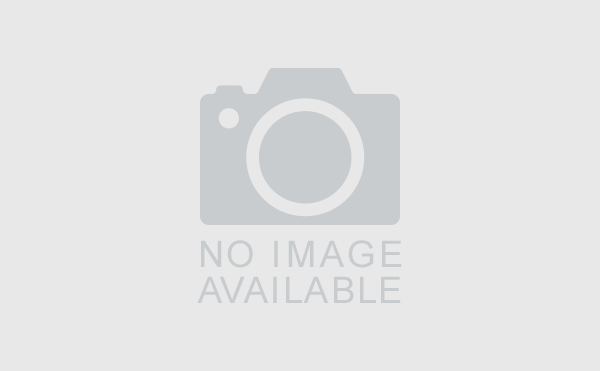今日のテーマはこちらです↓
=============
受験生・保護者に知っておいてほしい!
<国公立の2次試験対策>
=============
国公立2次試験まであと14日!!
2次試験対策のキモ。
過去問の使い方について
お伝えしていきます!
今回はこちら↓
「過去問は何年解けばいいですか?」
毎年多くの受験生や保護者の方から
ご質問いただきます。
答えはこちら ↓
『最低2〜3年。できたら5〜6年分解きたい』
過去問の一番の軸は、
○ その大学が出す問題の癖を掴むこと
です。
2〜3年分解けると、
だいたいの傾向が掴めてくる
と多くの生徒が言っています。
できたら5〜6年というのは、
その大学の出題傾向をより
多く把握できるからです。
よくあるのが・・・
● 今年は傾向がガラッと変わって対応できなかった
いや、そういうのいらないから・・・
変わるんだったら変わるって言ってよ!
と思っちゃいますよね・・・
傾向が変わった年の
生徒の落胆ぶりったらすごいです 汗
ただ!
大学側にとっては
こっちの気持ちなんてお構いなしです 涙
それでですね、
傾向が変わると言っても
目新しいものに変わるって
そんなにあることではないんです
過去に出されていた問題に、
似せて出してくることがあります。
4〜6年遡ると傾向が違う問題に
触れることもできるので、
その大学の傾向パターンを
多く知ることができます。
ただ、絶対ではないです。
過去問はあくまで「過去問」
過去に出されているので、
同じ問題が出ることはありません。
あくまで「傾向」を知るための道具。
なので
「2〜3年解いて傾向を把握する」
まずはここから始めていきましょう!
.png)