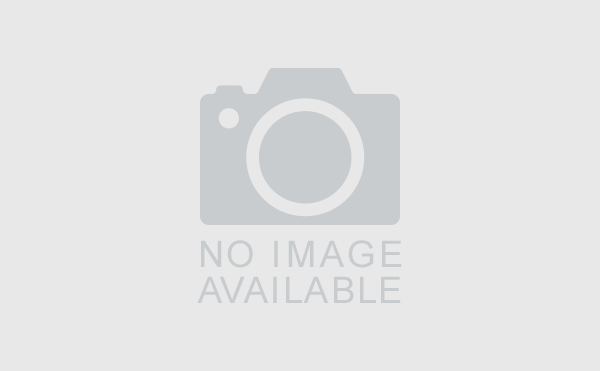今日のテーマはこちらです↓
=============
受験生・保護者に知っておいてほしい!
<過去問から学ぶこと>
=============
過去問からこの情報を収集すべし!
1、解けた問題は、なぜ解けたのか
2、解けなかった問題は、どうしたら解けたのか
ということで、
前回は「1」について解説をしました。
今回は、
「2、解けなかった問題は、どうしたら解けたのか」
を詳しくお伝えしていきます。
それでは、行ってみましょう!!
〜過去問は腐っても過去問〜
いきなりなんだ!?
って感じですよね。
解けなかった問題があったときは
この言葉を思い出して欲しいんです。
どうして??????
● 解けなかった問題そのものにこだわる
人が多いからなんです。
解けなかった問題そのものを解けるようにすることは大切です。
けど、
○ 同じ問題はその大学では出題されない
ということを認識しておいてほしいんです。
(化学は使い回しもあるようですが・・・)
・Aという問題が出た
・Aという問題そのものを解けるように努力する
こうすると、
全く同じ形で出題されないと
解けない頭になってしまいます。
「過去問は腐っても過去問」
解けるようにした問題と
同じ問題は出ないのです!!!
文字で見ると当たり前のことを言っているんですが、
これをやっている人はひじょーーーーーに多いんですよ〜
じゃあどうしたらいいのか?
ヒントはこちら。
○ ”解けるようになった問題で使った考え方”で解く問題は出題される
・
・
・
具体例を出しますね。
〜問題〜
( )many of the attendees were late because of traffic,
the president’s presentation began on time.
( )に入る適切な選択肢を選べ。
A: As soon as
B: So that
C: Rather than
D: Although
正解:D
〜NGな考え方〜
答えは、Dなんだな。OK~
〜OKな考え方〜
カンマの前後ともに、主語+動詞の形がある。
( )には2つの文を繋ぐ接続詞の働きをするものが必要。
さらに文の意味を読んでみよう。Dが正解になる。
違い、わかりますか??
OKな考え方は、
・どこに注目するのか
・使う知識はなんなのか(文法?語法?単語?イディオム?)
・そのほかに考える必要があることは何か(文脈をみる)
ということをしています。
こういう考え方までできると、
単語や文章が変えられても正解できます。
さらに、
「確実に」正解することができるようになります。
・どうしてその答えになるの?
・何をヒントにその考え方を選べばいいのか
間違えた問題こそ、
これら2つのことまで考えられるようにしておきましょう。
ここまでできると、
過去問から全てを学び尽くすことができますよ!
.png)